| 若手懇談会>前回の講演会
第158回講演会報告 第158回若手懇談会開催報告
[講演1]「「ガラスの街とやま」40年の取組について」 富山市企画管理部文化国際課主幹 ガラスの街づくり推進担当
富山市は約40年にわたり「ガラスの街とやま」として、アートとしてのガラスの浸透を推進する独自の取り組みを続けている。歴史的には1985年に市民向けのガラス工芸コースが開設され好評を博したのをきっかけに、1991年に本格的な学びの場として富山ガラス造形研究所が設立され、1994年に製作の場として富山ガラス工房が併設された。2015年には製作されたガラスの作品を鑑賞する場として富山市ガラス美術館が設立され、教育の場、製作の場、展示・鑑賞の場と施設が市内に整えられた。その結果、1つの街でガラス作家の育成から自立までが可能な環境となり、例えば安く使用できるガラス工房の工芸用設備を求め、ガラス作家の富山市への定住率も増加するなど市政への好循環もみられるとのことであった。また、市民へのさらなる「とやまガラス」ブランド浸透を目指し、ガラスのペーパーウェイト体験の小学校の卒業制作への導入や、街のホテルや富山駅、富山空港での作品展示を行っているとのことであった。 写真1 ガラス美術館前での集合写真 [講演2]「富山ガラス造形研究所におけるガラス造形教育〜ガラスアートの可能性〜」 富山ガラス造形研究所所長 富山ガラス造形研究所では日本で唯一の公立のガラス専門学校であり、基礎からガラス造形を学ぶ造形科が2学年(各16名)、実践的な制作活動を行う研究科が2学年(各5名)から成る。これまでに540名程の卒業生がおり、70%程はガラス作家として関わっているとのことであった。国外からの入学者も多いが、それは、富山のガラス工芸が、小樽や琉球と比べると歴史は浅いものの、産業・文化だけでなく教育基盤も有する点が世界でも特徴的な地域だからとのことであった。特にここ10年は実践的な教育に力を入れており、工芸の製造技術だけでなく、何を作るか、なぜ作るか、社会に作ったものの価値をどう示すかといった、卒業後の作家としての自立性を養う教育にも力を入れている。近年は特に学生の入学目的も多様化しており、学外からの特別講師招聘も含め、目的や目標に応じたサポート体制を整えているとのことであった。 最初に訪れた富山市ガラス美術館では学芸員の方の説明を聞きながら、常設展の中からいくつかの作品を鑑賞させて頂いた。絵の具で着色した作品や、パートドヴェールといったガラス粉を焼成して作製する技法を用いた作品、ガラスの屈折を利用した作品など作家毎に様々な表現方法を取り入れている作品が並んでおり、見て楽しみながら、どのように製作されているのか各々考察を巡らせながら鑑賞を行った。 本見学にあたり、見学を受け入れて下さった担当者様・先生方、ご講演頂きました先生方に大変感謝いたします。 以上 |
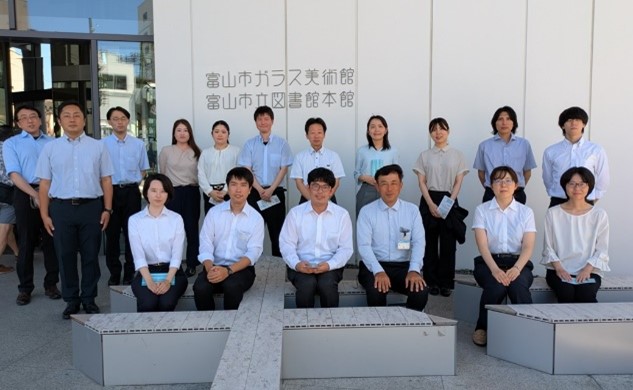
 写真:2 富山造形研究所での集合写真と内部の様子
写真:2 富山造形研究所での集合写真と内部の様子